子育ても学びも、「わからない」を放置しない ーRISUとKids Publicの「見守り」と「気づき」とはー

【はじめに】
「Kids Public」は、スマホ一つで専門医に相談できるサービス
Kids Publicは、育児中の「これって大丈夫?」という小さな不安に寄り添うオンライン健康相談サービスを提供しています。スマートフォンから24時間365日アクセスでき、小児科・産婦人科の専門医と助産師に直接相談できるのが特長です。
企業の福利厚生や生命保険の付帯サービス、自治体の子育て支援事業として導入されており、対象となる方は無料で利用できるケースもあります。
「こんなこと聞いていいのかな」とためらってしまうような悩みも、気軽に専門家へ相談できる仕組みに。子育ての正解が見えづらい時代に、家族以外の「第三のサポーター」として、保護者に安心を届けています。
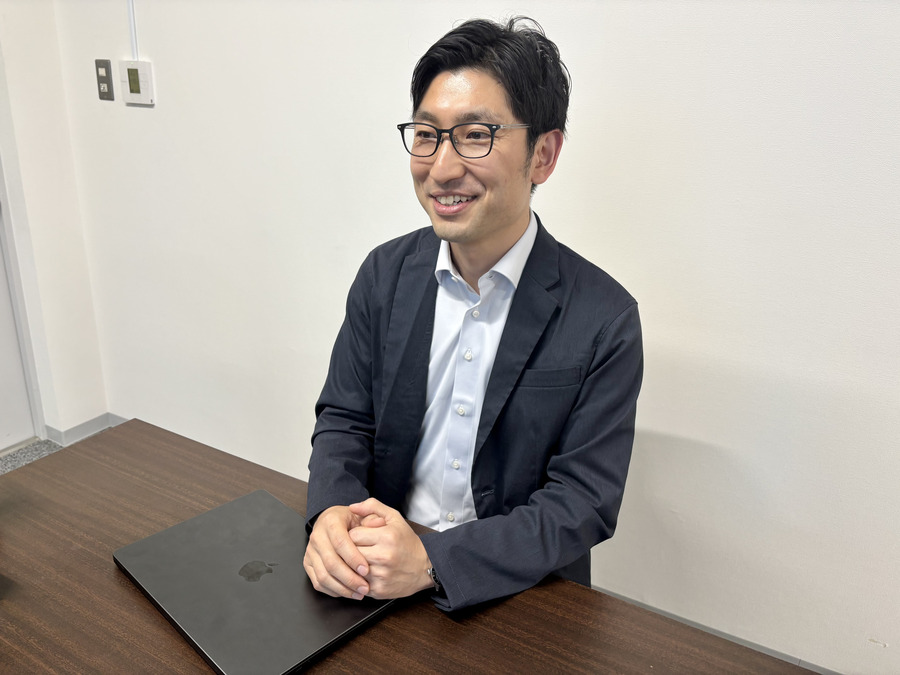
もっとも多いのは病気ではなく「育児」の相談
Kids Publicで寄せられる相談の中で、最も多いのが「育児に関する悩み」です。
たとえば、以下のようなものがあります。
- 「赤ちゃんが生まれたばかりだけれど、飼い犬と同じ部屋で過ごしていて大丈夫?」
- 「うつ伏せ寝が危ないと聞いたけれど、ずっと見張っていないといけないの?」
このように、日常の中でふと生まれる疑問が多く寄せられています。医学的に重篤な問題ではないからこそ、かえって誰に聞いたらよいのかわからない、そのようなグレーゾーンの悩みにこそ、専門家の一言が心の支えになると橋本さん。
では、そもそもなぜこうしたサービスを立ち上げようと思ったのでしょうか。
背景には、橋本さん自身が小児科医として現場で感じたある「違和感」がありました。
【子育ての課題】
子どもの「学び」と「育ち」を守るために親子の孤立をなくす「相談の場」の役割とは
子育ての現場において、「子どもだけでなく、親の孤立も見逃さない」ことが大切だと語る橋本さん。小児科医としての現場で感じた違和感が、いまの活動の出発点になっていると言います。
子ども病院での経験から見えた「親子の孤立」という課題
橋本さんが小児科医として働いていたある日、病院を訪れた母親から「自分が子どもにケガをさせてしまった」と涙ながらに来院したという出来事がありました。
医療機関は「基本的に来てもらう」のを前提とした場所。でもこの経験から、「こちらから手を差し伸べる仕組み」の必要性を強く感じました、と橋本さんは振り返ります。
この気づきが、スマートフォンを使って産婦人科や小児科の医師に直接相談できる「オンライン健康医療相談サービス」の原点になったとのことです。
時間や場所の制約を越えて、不安に寄り添う仕組みは、いまや全国の自治体や企業にも広がり、多くの家庭に安心を届けています。
小児科医は「病気を見る」だけじゃない
小児科というと、発熱や咳などの病気を診てもらう場所というイメージが強いかもしれません。しかし橋本さんは、健診の現場では子どもの発達だけでなく、家庭環境や保護者の様子にも注意を払うといいます。服装の清潔さ、表情、身体のあざなど、子どもを通して家庭の状況が見えることも少なくないそうです。
もしも「このご家庭、少し気になるな」という兆しを感じた場合は、行政や地域の支援機関につなぐなど、早期対応を心がけているとのこと。
「子育ては親ひとりの責任ではなく、社会全体で見守ることが重要です」と橋本さんは話します。
子育てはみんなで「見守る」・「ひとりで抱えない」環境づくりが大切

日々のちょっとした不安を気軽に相談できる環境は、保護者にとって心の支えとなり、子どもにとっても安心して挑戦できる土台になります。
RISUの学習サポートでも、「保護者がすべてを背負わなくていい」という安心感が、子ども自身の自立と成長を後押しすると実感しています。
RISUでは、日々の学習進捗や到達度を保護者にメールで通知する仕組みがあり、「満点を取るまでよく頑張ったね」といった声がけのヒントになる個別アドバイスもお届けしています。
たとえば、「すべてのステージで合格点に達し、粘り強く再挑戦する姿勢が見られます」など、お子さまの努力を適切に評価できるようサポートしています。
またRISUの学習データからは、「家族2人以上で見守っている家庭では、学習の進みが1.5倍に向上する」という結果も。お母さんだけでなく、お父さんや祖父母も一緒に関わることで、子どものやる気と継続力が自然と育まれます。
RISUは、家庭のなかに「学びの見守りチーム」をつくることで、子どもが安心して学び続けられる環境づくりを支えています。
保護者や周囲の見守りが、子どもの挑戦を支える土台になる。そうした「第三の視点」や「ほどよい距離感」の支援は、学びだけでなく、子育て全般にも共通する大切なテーマです。
「これってどこに相談すれば…?」迷いや不安に寄り添うサポート体制
子育てや学習で生まれる小さな不安。その背中をそっと押すのが、頼れる第三者の存在です。ここでは、医療と学習の観点から、中立的なオンライン支援の役割についてお伝えします。
医療における「迷い」に応える中立的サポート
「子育て中の保護者にとって、「誰に聞けばいいのかわからない」という迷いは日常的に起こります。たとえば、子どもの肌にできた湿疹は小児科なのか皮膚科なのか、あるいは薬局で済むのか、そうした判断に悩む場面は決して珍しくありません。」と橋本さん。
「Kids Publicのオンライン相談では、症状や状況を聞いたうえで、適切な診療科の選び方や医療機関の探し方をアドバイス。病院の専門性の見極め方や、受診の優先度など、中立的な立場から丁寧にサポートします。医療機関では直接聞きにくいことでも、第三者的な視点だからこそ相談しやすく、安心感を得られるのです。」
学習における「つまずき」を見逃さない見守りの仕組み
一方、学習の場面では、「これって大丈夫かな?」という小さな不安が、気づかないうちに大きな悩みに発展することがあります。誰にも相談できずに抱え込んでしまえば、親も子も、どんどん追い詰められてしまうかもしれません。
だからこそ、悩みが深くなる前に寄り添う仕組みが必要です。RISUでは、学習中の小さなつまずきを自動で検知し、タイミングよくサポート動画を配信。子どもが一人で悩みを抱え込む前に、適切なヒントや励ましを届けます。
小さな不安の段階で、そっと背中を押す。そんな「見守りの仕組み」が、安心して続けられる学びの環境をつくっています。
こうした「迷いや不安」に寄り添う支援体制は、全国的に求められる一方で、そのニーズや活用のされ方には地域ごとの違いも見えてきます。次に、オンライン支援を取り巻く「地域特性」に目を向けてみましょう。
【オンライン医療の可能性】

同じオンライン支援でも違う「地域ごとのニーズ」
同じ、オンライン相談でも、求められる形は地域によってさまざまです。
医療や学習のオンライン支援が果たす役割も、住む場所や人との関係性によって変化します。ここからは、地域特性に応じた支援のあり方について考えてみます。
地域特性によって変わる「孤立」のかたち
オンライン相談が担う役割は、地域によって異なります。
たとえば地方では、医療機関や専門職(助産師、産婦人科、小児科医など)がそもそも少ない・存在しない地域もあり、妊娠・育児に関する初期相談のハードルが高くなりがちです。こうした場所では、「まず誰かにつながる」ことが支援の第一歩であり、その役割をオンラインが担っています。
一方で都市部においては、「誰が隣に住んでいるかわからない」といった人間関係の希薄さから、育児の孤立が深刻になりやすい傾向があります。こうした背景をふまえ、都市部でもオンライン相談が“つながりの起点”として求められているのです。
また、地方特有の「地域コミュニティの濃さ」が、かえって相談のしづらさを生むこともあります。身近な行政職員や知人が相談先であるがゆえに、声を上げづらくなる保護者も少なくありません。その点、完全に関係性のない相手とつながれるオンライン相談は、貴重なセーフティネットとして機能します。
RISUは「オンライン完結 × 個別対応」
子育ての環境が地域によって異なるように、子どもの学び方やサポートのあり方もさまざまです。
学習面では、地域による教育格差や支援体制の違いが課題となる一方で、RISUは全国どこでも均一な学びの質を提供できる仕組みを整えています。
RISUの特徴は、学習データを活用したピンポイントの個別対応にあります。
すべての学習がタブレット上で完結し、子どもの理解度やつまずきを細かく分析。問題ごとの滞在時間や誤答傾向をもとに、必要なタイミングでヒント動画や解説を配信します。
首都圏では対面塾も展開していますが、多くの家庭ではこのオンライン完結型の学習スタイルで、場所を問わず学びを進めることができます。
こうした「オンラインだからこそできる支援」は、いつでも・どこでも相談できるKids Publicの取り組みにも通じるもの。
教育でも、医療でも、子ども一人ひとりに合った支援が「ひとりにしない仕組」として広がっています。
【さいごに】

子育ては「ひとりで頑張らなくていい」
医療も学びも、「見守る仕組み」が支える時代へ
「子育てには村が必要」ということばがあるように、親だけに負担をかけない仕組みづくりがいま、医療や教育の現場で進んでいます。
Kids Publicが提供する「産婦人科・小児科オンライン」では、家庭での小さな悩みや迷いに、いつでも専門家が寄り添える体制が整えられています。これは、親子が孤立しない社会をつくる第一歩でもあります。
RISUもまた、子どもの学びにおいて「ひとりにしない」スタンスを大切にしています。自宅での学習を支えるのは、タブレットを通じたRISUの個別最適なフォロー。つまずきを検知したタイミングで自動配信されるヒント動画、そして保護者に届く学習レポートなど、家庭での見守りを支援する仕組みが整っています。
さらに、RISUでは「家族で見守る学び」を推奨しています。親が隣で勉強を教える必要はありませんが、子どものがんばりを認めたり、つまずきに一緒に気づいたりすることが、学びの安心感につながります。祖父母やきょうだいなど、多様な家族のかたちのなかで、子どもの成長を見守るスタイルが広がっています。
「医療も教育も、孤立させない”という考え方」オンラインの力を活用して、親子に寄り添う仕組みが、少しずつ日常の中に根づき始めています。
現在のところ、同様のサービスはまだ限られており、子育て世代のもうひとつの選択肢として、より多くの方に知っていただければ幸いです。
「これって相談していいのかな?」という迷いを手放し、気軽に頼れる存在として、今後も広がっていくことを目指しています。
現在、Kids Publicのサービスは個人への直接提供ではなく、企業や自治体を通じてのご利用となっています。福利厚生の一環として導入する企業や、保険会社・人材サービス会社の付帯サービス、あるいは自治体の子育て支援施策の一部として活用されています。
https://kids-public.co.jp/
※なお、サービスの利用可否はご所属の企業・ご加入の保険・自治体の取り組みにより異なります。あらかじめご了承ください。

橋本直也|株式会社Kids Public
ープロフィールー
株式会社Kids Public 代表取締役 / 小児科医
2015年にKids Publicを設立。スマホなどから産婦人科医・小児科医・助産師に相談できる「産婦人科・小児科オンライン」を運営中。医療者が社会とつながることで、子どもたちの健やかな成長により深く関わることを目指す。
「子育てには村が必要」という言葉を信念に、孤立しない子育て環境の実現に取り組んでいる。
























