「読む力」と「考える力」を耳から育てる音声学習のすすめ

「目が不自由な人が、本を読む手段がもっとあったら」
オーディオブック配信サービス「audiobook.jp」などを展開する株式会社オトバンク。
その創業の背景には、会長・上田渉さんの原体験があります。今回は、耳で学ぶことの価値や音声学習の可能性について、お話を伺いました。
【はじめに】
オトバンクについて

創業の原点にある「祖父との記憶」
祖父は緑内障で視力を失ってから亡くなるまでの20年近く、目が不自由なまま過ごしました。祖父は本が大好きで、本棚には読みかけの本がたくさんありました。その本たちはホコリをかぶって読まれないまま。
私が記憶している祖父の姿は、テレビの真横のソファに座って、音声だけを頼りに野球やニュースをずっと聴いている姿です。そんな祖父に向かって、私はひたすら話しかけていました。
そして、大学入学前に祖父を亡くし、「自分には何もできなかった」という想いを抱えながら就職活動を行うことになります。就職活動の自己分析のなかで「祖父のような方に貢献できないか」と考え、耳から情報を得る文化の可能性に着目します。
「耳で学ぶ・楽しむ文化」を広げたいという想い
当初は視覚障がい者の方向けの朗読サービスを考えていましたが、障がい福祉サービスは対象の範囲がどうしても狭くなるため、一般的に認知されにくく、結果として肝心の当事者に届きづらいという課題があります。そこで、まずは視覚障害者の方の周りにいる一般の方々に音で情報を得るという選択肢を広げれば、結果的に多くの人の助けになるのではと思ったんです。
それが「オーディオブック」です。
audiobook.jp
誰もが「耳で学ぶ・楽しむ」文化が広がれば、そこから自然に支援にもつながる。そんな仕組みを作ろうと、大学3年生のときに起業し、「聞く文化を広げる」ことを掲げ、オトバンクは動き出しました。
「聴くを軸に広がる情報」オトバンクの多面的展開
オトバンクは、オーディオブック配信サービスaudiobook.jpを中心に、「耳で聴く本のある暮らし」を提案しています。
audiobook.jpは現在、ユーザー数300万人以上。日本語コンテンツ数も日本最大規模で、ビジネス書から小説、自己啓発、語学まで幅広いジャンルを網羅しています。
BtoB向けの展開も進んでおり、社員研修や福利厚生として活用できる「audiobook.jp 法人版」は約200社の導入実績があります。
また近年では、企業内コミュニケーションを支援する音声サービス「社内ラジオ」も提供。経営者と社員の対話をプロのラジオ制作チームが番組化し、従業員のエンゲージメント向上に一役買っています。会社の話って、どうしても堅くなりがちですよね。でも、プロの制作チームが作るラジオ番組なら毎週楽しみにしてるという声が上がるんです。ちゃんと番組として面白く作れば、情報が心に届くし、記憶にも残ります。
さらに、企画制作チーム「スタジオオトバンク」では、音声に限らず映像制作や教育分野へのアプローチも強化。今後も「音を通じた学びやつながり」を広げるべく、多面的な展開を進めています。
【耳学習について】

音声で学ぶという選択肢「読む」以外の学びの可能性
読書するスピードや理解度には、目で文字を読むだけでなく、音に変換して言語として理解するというプロセスが関わっています。これは「音韻処理」と呼ばれ、読書や学習における重要な認知プロセスです。
音韻処理とは?
文字を読むとき、私たちの脳はまず目で文字を認識し、それを脳内で音に変換(音韻化)し、その音を言語として理解するという順番で処理を行っています。つまり、「見る→音にする→意味を理解する」という流れです。
このプロセスを経て、はじめて読書や学習内容を理解できるのです。読書スピードや内容の定着には、この音韻処理の効率が大きく関係します。
読書とは、目で見て(視覚)音で理解する(聴覚)ことで記憶しているというのがポイントとなります。
情報の受け取り方には「認知特性」が関係
人にはそれぞれ、情報を「理解しやすい方法」に違いがあります。こうした一人ひとりの特性のことを「認知特性」と呼びます。
たとえば、目からの情報が理解しやすい人(視覚優位)もいれば、耳からの方が理解しやすい人(聴覚優位)もいます。
とくに、読むことが苦手な人や、「ディスレクシア(読みの困難)」傾向のある人は、読書に強い負担を感じることがあります。さらに広く見ても、「読むのが遅い」「理解に時間がかかる」といった読書に向いていない層は、全体の7割にも及ぶことがわかりました。
こうした場合、音声で学ぶという方法が大きな助けになります。
音声学習は、苦手を補い、学びを助ける
そもそも人間は、赤ちゃんの頃から耳で言語を学び、あとから文字を習得します。
つまり、音声は私たちにとって本来なじみのある学びの手段。読むことが合わない人にとっては、視覚よりも聴覚の方が処理がスムーズな場合もあります。現代の学習スタイルは、文字・映像など視覚に依存したもの(動画、eラーニングなど)が多くなっていますが、自分に合ったインプット方法を選ぶことが、学びの効率を大きく変えます。
オーディオブックや音声教材の活用は、まさにその選択肢のひとつと言えるでしょう。
【読解力・思考力の育成について】
読解力を育てる「音声学習」の力
オーディオブックや音声学習は、「読解力」を育てる有効な手段です。
そもそも読むという行為は、目で文字を見て、それを脳内で音に変換(音韻処理)し、意味を理解するプロセスで成り立っています。
つまり、読解力とは「音韻処理」や「言語処理」を土台に、論理的思考や語彙力、背景知識が積み重なって育つ力です。
オーディオブックを活用し、音で「読む力」を鍛える
人には「認知特性」という個人差がありますが、実は人口全体の約70%が「音で理解するタイプ」の可能性があります。
このタイプの人にとっては、大量の音声を処理する経験がそのまま言語処理力のトレーニングになります。つまり、音声学習は、「読む力」の基盤を強くするともいえるのです。
海外では、ディスレクシア(読みの困難)を抱える人たちへの支援研究が進んでおり、音声学習の有効性が証明されています。私自身も、そこからヒントを得て「読む力を育てる音声トレーニングプログラム」を開発しました。
▼「超効率耳勉強法」
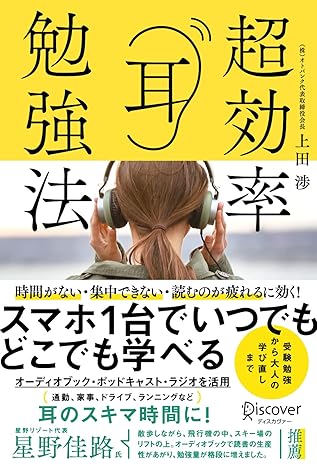
▼「超効率耳勉強法」 audiobook.jp
https://audiobook.jp/product/264892?srsltid=AfmBOoqfoWYrqgWgzUE67SkQPvEuR5XcwOlid_NwYc3AN8qFobXVX2Sr
実体験が示す音声学習の力〜偏差値30から東大へ〜
私は高校まで、偏差値30台でした。実は小学校の時に通っていた塾が、問題ができるとシールをくれる先生で、そのシール欲しさで勉強をしました。その結果、名門校と呼ばれている私立の中高一貫校に合格しましたが、中学校では勉強してもシールがもらえない(笑)。
なぜ勉強しないといけないのかと先生に聞くと「大学に入れない、就職できない」みたいなことを言われて、身も蓋もないと感じ勉強をボイコットしました。
中1から高3までは全く学力が向上せず、記述式のテストは、まぐれで当たった5点が精一杯でした。
ある日、東大志望の同級生たちに「なぜ勉強しているのか?」と聞いて回った結果、「旅行に行ける」「おこづかいが上がる」といった、ご褒美目的の答えばかりだったことに強い衝撃を受けました。「こんな仕事をしたい」「こんな先生に学びたい」というビジョンをもつ人は誰もいなかったんです。
「このままでは日本が危うい。教育を変えなければいけない」と強く感じた私は、政治家になって教育改革をしたいと思うようになりました。教育改革で戦う相手は文部科学省の官僚ということになるので、まずは官僚の経歴を調べてみると東大卒が多く、自分も東大に行かなければ始まらないと決意しました。
しかし現実は厳しく、まず“読んでも理解できない”という壁に直面します。そこで始めたのが、徹底的な音読トレーニングでした。毎日同じ文章を100回以上読み、ふりがなをふって、音で理解する練習を続けました。
そうして「音から入る学習」を重ねるうちに、文章構造や意味の理解も自然に深まり、他の教科にも好影響が出てきたのです。
言語理解力が高まると、教科書や参考書の吸収スピードも飛躍的に上がり、東大合格を果たすことができました。
音声学習は「苦手」を突破する鍵になる
こうした経験をもとに、音声学習を中心としたトレーニングプログラムをカリキュラムとして提案しています。とくに「聴覚優位」の認知特性をもつ70%の人にとっては、効果が非常に高いです。
さらに現在は、より精度の高い認知特性サーベイの開発も進めています。
【オーディオブックの活用について】

忙しい現代人にこそ「耳読書」がおすすめ
オーディオブックは、特にすきま時間を活用したい方におすすめです。
たとえば、仕事や育児でまとまった読書時間が取れない社会人や小さいお子さんをお持ちの方、読書に苦手意識がある方にとって、耳で聴く読書はとても相性が良い手段です。
音声を通して言語に触れる機会が増えると、言語処理力のトレーニングにもつながります。慣れてくると倍速再生(私自身はビジネス書を3倍速で聴いています)も可能になり、脳の処理スピードも飛躍的に向上します。
親子で一緒に聴く楽しみ方
子育て家庭では、親子で一緒にオーディオブックを聴く時間をつくるのも効果的です。絵本の読み聞かせも良いですが、親が読むにはちょっと大変な名作文学などは、オーディオブックで一緒に楽しむのがおすすめです。
あとは音声での「早口言葉チャレンジ」や「交互に音読してみる」など、遊び感覚で言葉に触れる工夫を取り入れるのもおすすめです。
オーディオブックで国語力アップ
実際に、私の知人の子どもが国語に苦手意識を持っていたのですが、「オーディオブックならいくらでも聴いていい」とルールを決めて、好きな作品をたくさん聴かせたところ、いつの間にか4倍速で聴けるようになっていました。
驚いたことに、親には理解しづらいスピードでも、子どもは内容をちゃんと把握しており、語彙力や読解スピードが劇的に向上しました。その結果、国語の偏差値も上がり、全国トップクラスの成績を収めるようになりました。
「読む力」が前提となる学力テストにおいて、「読むスピード」や「聞いて理解する力」があることで、設問を早く読み終えて考える時間に余裕が生まれる、これは大きなアドバンテージです。
文字+音声の併用で語彙の習得も加速
語彙力をしっかり伸ばしたい場合は、「文字を目で見ながら、同時に耳で聴く」というスタイルが最も効果的です。聴覚と視覚の両方を使って言語に触れることで、記憶の定着も深まりやすくなります。
お子さんの認知特性を理解し、それぞれに合ったスタイルでサポートしてあげることで、音声学習の効果はさらに高まります。
【最後に】
耳で学ぶ文化をもっと広げたい
私たちオトバンクは、「聴く文化を広げる」ことを理念に、耳で学ぶ・耳で楽しむ環境をもっと多くの人に届けたいと考えています。特に、耳での勉強や音声学習は、これからの時代にますます重要になっていくと確信しています。
RISUのみなさんと一緒に、音声トレーニングやリスニングを活用した新たな学びの形を広げていけたら嬉しいです。現在、教育プログラムとしての活用も視野に入れた取り組みを準備中です。ご興味のある方は、ぜひ一緒にチャレンジしていきましょう。

上田渉|株式会社オトバンク
ープロフィールー
株式会社オトバンク代表取締役会長。日本オーディオブック協議会常任理事。耳活アドバイザー。東京大学経済学部経営学科中退。2004年にオトバンクを創業し、代表取締役に就任。自身が受験時代の勉強法として活用した音声学習もヒントに、オトバンクを創業。会員数300万人のオーディオブック配信サービス「audiobook.jp」を運営。著書は『超効率耳勉強法』『脳がよくなる耳勉強法』等多数。
























